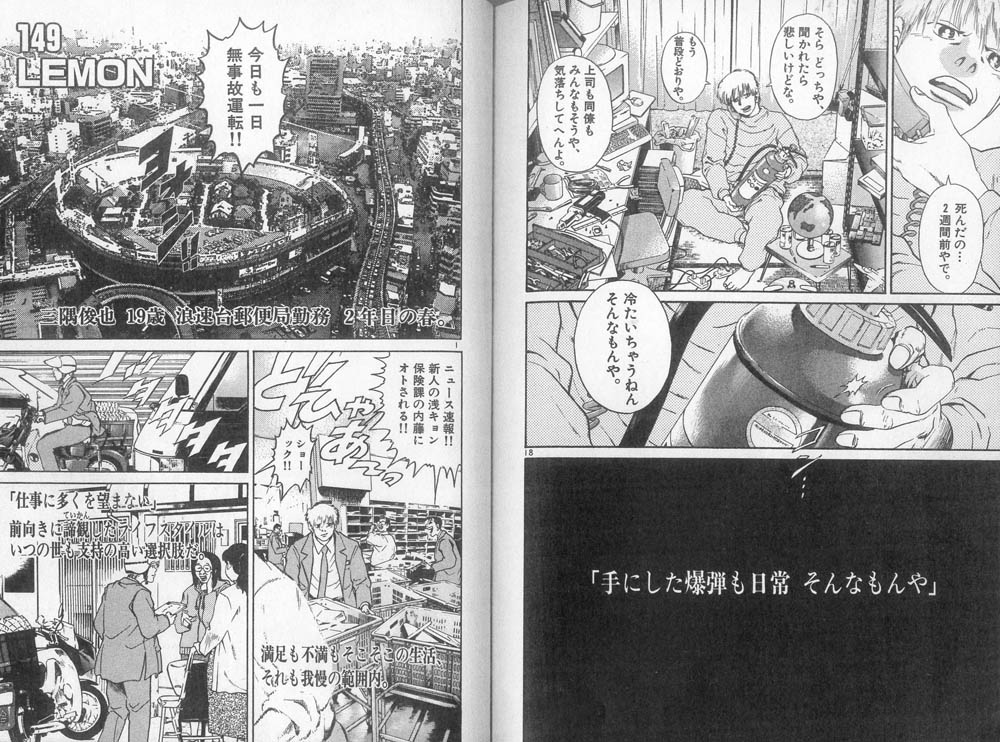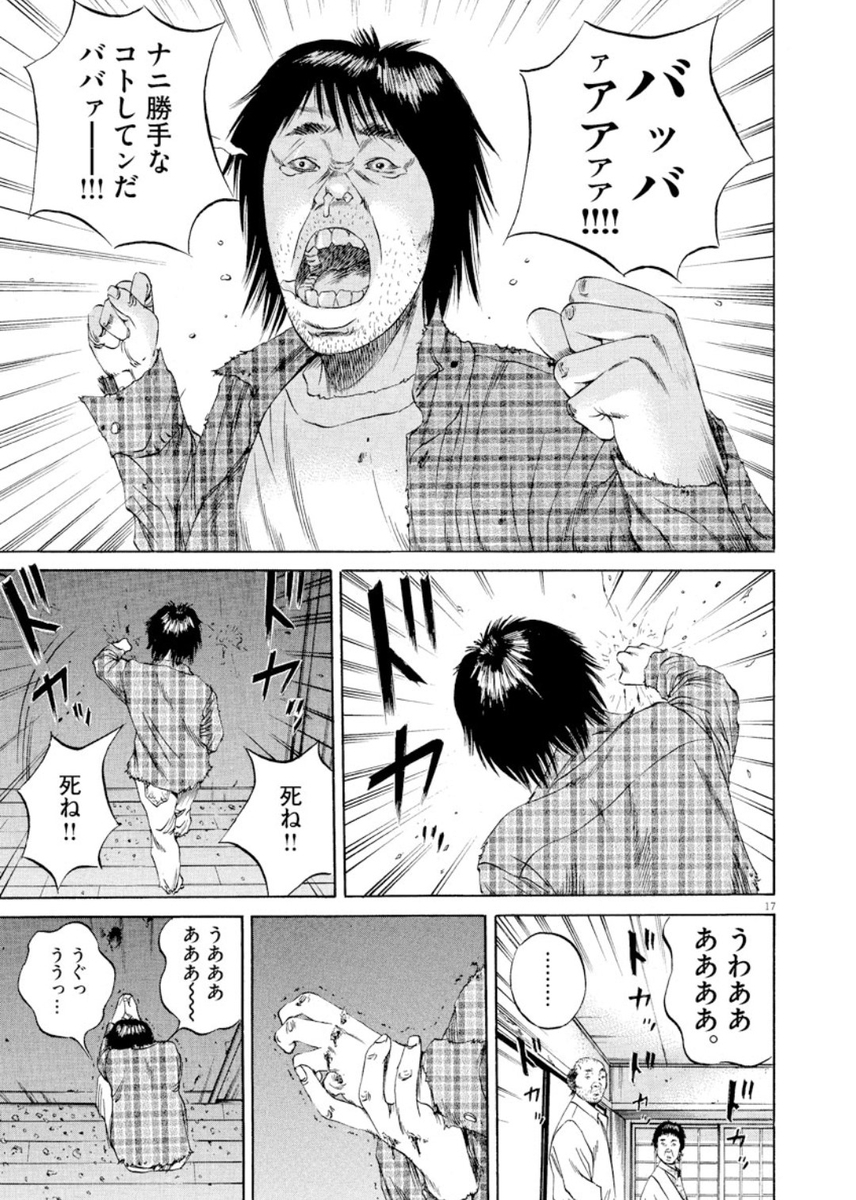グルメブログを運営していて、最近はこちらの方の更新に力を入れているが。
もう食べ歩きができないほどに、困窮してきたな…ラーメンとか1000円台で収まる店なら、たまに行けるが。
居酒屋とかそういう店は、月に1回行けるかいけないか…って感じだ。
低所得の人間は、外食という趣味も楽しむことはできない。
ザ・ノンフィクションの「東京キッチンカー物語」で、勝負してた人みたいにね。
自分も収入的には、不良在庫のカビたパンを食わないといけないぐらいの身分ではある。
番組に出てた若者が「自分の価値を人に決められたくない」と言ってた。
わかるねぇ、俺もそれで脱サラしたんだよ。
いや、違うな。
そんな立派な動機じゃなかった。
所得的には去年、200万もいってないし。
しかも実家暮らしで家賃が浮くわけとかでもない…。
仕方ないので節約のため、家グルメを満喫させるようにもシフトしていくことを考えた。
まあカビたパンは嫌だけどな。
発がん性物質とかあるみたいだしね。
昨日の10月19日土曜日から、プライム感謝祭が始まってるみたいだ。
プライム会員にはなっている。
prime videoが見たかったというわけではなく、通販で無料で物を買いたいというのが理由だったかな。
で、このプライム感謝祭は、ポイントがいつもより付くみたいなので。
家グルメで節約生活にシフトするため、何か欲しいものを買い込んでおくいい機会ではある。
というわけで。
自分が調べ上げたグルメアイテム、お取り寄せグルメを、以下に羅列しておこう。
ほぼ自分のための備忘録ではあるものの、記事を読んでくれる人にも気になるアイテムがあれば幸い。
また、リンク先はアフィリリンクになってるので。
欲しくなっても、踏んで飛んで、そのページ経由で買う必要はない。
文字情報、商品情報だけ参考にしてくれれば。
そりゃあリンク先から買ってくれたら嬉しいが、しかし、この記事の本筋ではない。
あくまで「自分がプライム感謝祭とか、Amazonでいつか買いたいもの、アマゾンで見つけた面白い商品のリストをまとめる」のが主目的だから。
貧乏だが、まだ自分は乞食や物乞いの類にまでは落ちぶれてはいないと信じたい。
よくツイッターとかで「#Amazonプライム感謝祭」とかハッシュタグ付けてアフィリンク飛ばすスパム行為してる輩がいるが、俺は違うぞ!と。
ドリンク
(1)【お子様から大人まで/ノンアルコールスパークリング】ラシャス ジュドポムぺティアン フランス ノルマンディー産の林檎のストレート果汁100% 750ml〈砂糖・甘味料・香料・酸化防止剤不使用〉
オーガニックで美味そうなシャンパンだ。クリスマスは、ケンタッキーで買ったチキンとか、コージコーナーとかシャトレーゼで買ったケーキとか並べてね…このノンアルのシャンパンで、家族団らんの時間を過ごす。
そんな未来が欲しかったな…。
(2)天然生活 バタフライピーハーバルブレンドティー (50包) ティーバッグ オレンジピール レモングラス スペアミント
青い紅茶?どんな味がするんだろうか…バタフライピーティー、ちょっと飲んでみたい。
(3)【かき氷やアイスにも】 LEJAY(ルジェ) サントリークレーム ド ピーチ [ リキュール 700ml ]
ピーチリキュール、アイスとかかき氷にかける?お洒落だな、これは節約グルメではないが、生活を豊かにしてくれそうではある。ノンアルじゃないのか。
(4)交洋 カールユング スパークリングドライ 白『ノンアルコールワイン アルコール分0.5%未満』 750ml
アルコール0.5%未満のワイン、これなら自分も飲めるかもだ。
これカルディにもあるのか。値段比較しないとだ。
(6)神戸居留地 アップル ジュース 100% 缶 185g ×30本 [ 果汁100% 常温保存可 りんごジュース 国内製造 ]
この神戸居留地っていうメーカーの飲み物、なんか美味そうなんだよな。飲んだことないけど。
(7)ヤマモリ 炭酸割り専用FRUIT VINEGAR ザクロ 500ml
ヤマモリってこういうのも出してるんだ。
パスタ・麺類
(1)GAROFALO 明治屋 ガロファロ シグネチャー スパゲッティーニ 1.7mm 500g×6個
パスタは貧乏人の必須アイテム。
ガロファロシグネチャー、名前がカッコいいので、食ってみたい。
(2)キユーピー パスタソース あえるパスタソース 香ばし海老のペペロンチーノ
パスタソース、美味そうだ。こんな味が出てたのか。
食感をたのしむスパゲッティ、歯ごたえぷりぷり、と包装紙の表に書いてある。バリラとかレガーロとかは知ってたけど、これは知らなかった。ちょっと食べてみたい。
(4)ブルダック炒め麺 味比べ20袋セット(2種類×10食ずつ) (クアトロチーズ×カルボ)
韓国料理か?これは安い。具はなさそう…。
カレー・レトルト食品
カレーやレトルトも貧乏人の必須アイテム。
昔、ペンションでリゾートバイトしていた時、経営難なのかオーナーが出してくれる昼飯のまかないが。
毎日レトルトカレーだったなぁ、手間いらずで誰でも作れるし、金持ってない人が食ってるイメージ。
(1)【Amazon.co.jp限定】 ハウス カレー百名店全国巡りセット 選ばれし人気店9種ストック用BOX付きセット (ラムキーマカレー、キーマカレー、バターチキン、芳醇チキン、欧風 ビーフ、黒担々、スリランカカリー、北海道産野菜ポーク、欧風ポーク) 【セット買い】 ×9個
カレーストックボックスが貰える。いいよな。
(2)エスビー食品 S&B 赤缶カレーパウダールウ 中辛 152g
赤缶って何?と気になってる。小麦粉不使用なのも潔い。
味が気になるね。
(4)MCC エム・シーシー食品 小野員裕の鳥肌の立つカレー チキンカレー 200g
野菜とスパイス、粗塩だけで作った?チキンが入ってるなら鶏肉のブイヨンも出てるだろうよ。
小野員裕氏、今年死んでしまったんだよな…まだ64歳なのに、たまにブログ読んでたけど。
【訃報、その後】 - 元祖 カレー研究家 小野員裕
(5)エスビー食品 ごろごろ北海道野菜のビーフカレー 200g×10個
大きめサイズにカットした北海道産のじゃがいも、にんじんを具材に使用したオーソドックスなビーフカレーです。20種類の国産野菜を圧力釜でじっくり煮込んだブイヨンでコクのある味わいに仕上げました。…とあるから、健康によさそうな印象。
(6)丸美屋食品工業 1/2日分の野菜が摂れる 海老のビスク(カップスープ) 95.2g
これ食ってれば野菜わざわざ食わなくていいかぁ?
(7)からだ満足スタイル エスビー食品 からだ満足STYLE 鶏ひき肉と3種の豆のキーマカレー中辛 180G ×6箱
ひよこ豆、レンズ豆、レッドキドニーのふくよかな旨み。クミン、コリアンダーなどのスパイスが香るキーマカレーです。
手軽においしく1食分のたんぱく質が摂取できます。…豆かぁ、豆のカレーで肉を超えるのはなかなか難しい印象。
これは高級品だな…上野御徒町に店舗ある、まだ食べに行ったことないけど。
(9)くせになるこだわりのスパイス&オイルカレー (フレーク)×4セット
動物性の油脂や動物性のブイヨン・エキス等、動物性原料を使用せず仕上げたカレールウ…いいね。
(10)いなば食品 いなば ガパオチキンバジル 115g×24個
これは食費、抑えられそうだよな。この缶詰に玉子焼きを添えればガパオライスになるだろうし、炒り卵ならばそぼろご飯になる。本場タイで製造ってのもいいじゃない。
24個もいらないな。
楽天お買い物マラソンで買おうかな…1個単位で売ってる店もあるし。
1食分の野菜が取れる…いいじゃない。健康的なレトルトカレー、すばらしい。
これにキッチンオリジンとかで揚げ物買ってトッピングすれば、500円以内で栄養的にも食べ応え的にも満足できるカレーが作れそうだな。
上尾にある「娘娘(にゃんにゃん)」のカレーを再現したとか。町中華のカレーね、また食べに行ってみたい。
(13)HENAFF (エナフ) パテ・ド・カンパーニュ(田舎風のパテ) 78g 缶 【フランス産 豚肉 使用】【発色剤不使用】
パテ・ド・カンパーニュ、豚肉の加工品か。
パンだな、白飯には合うイメージが湧かない。
ナッツ
食はこ、ってメーカーのナッツ。
ナッツはタンパク質や栄養素も多くてダイエットにもよさそうだからね。
www.kojima-ya.com楽天でも売ってるが、パッケージのデザインがいいね。
(2)U.S.スーパーフード7種ミックスナッツ 1.008kg(28g x 36袋) 小分けミックスナッツ アメリカ直輸入 素焼き (アーモンド・くるみ・ピーナッツ・ピーカンナッツ・ピスタチオ・レーズン・クランベリー)便利な小分けタイプ
スーパーフード7つ食ってれば、飢えても大丈夫な気がする。印象だけど。
カリフォルニア堅菓、ってメーカーが出してるナッツ。
黄金生くるみ、普通のくるみよりすごそうなイメージ。
(5)毎日美容ナッツ 小分け ミックスナッツ 無塩 ドライフルーツ 豪華5種 (アーモンド/くるみ/マカデミアナッツ/パパイヤ/パイナップル) 自然食堂 健康 食塩不使用 国内製造 個包装 20g×10袋
健康によさそうなのがいいね。
デイリーナッツ、毎日食べましょうってことかね。
(7)ミックスナッツ 3種類 1kg 徳用 生くるみ 素焼きアーモンド 素焼きカシューナッツ オイル不使用 無塩 無添加 / 3G CARE
この3G CAREのナッツ、確か空気を抜いてパックされてたのがいいなと思ったことあったな。
調味料
(1)シェフズチョイス ヒマラヤ岩塩&ペッパー ミル付き オーガニック原料使用 Pink salt & pepper with Grinder (1:ブラックペッパー)
シェフズチョイス、パッケージのデザインも良い感じ、かけるとメシがうまくなりそう。
美味しそうなジャム、パンに付けて食べたい。
(3)Nutella FERRERO(フェレロ) ヌテラ 350g
ヨーロッパの食卓ではすっかりおなじみのフェレロ社のヌテラ。 世界各国の子供達に愛されてます。 香ばしいヘーゼルナッツのチョコレートスプレッド。 カルシウムや鉄分を含んだ栄養バランスの優れたスプレッドです! パンに塗るだけではなく、製菓材料などにもご利用できます。…とな。
米、麦、大豆を使ってない醤油。アレルギーのある子ども向けか?どんな味がするんだろう。
(5)生はちみつ専門店 MY HONEY からだに優しいイヌリンはちみつ チューブボトル 500g×1本 ハンガリー産アカシアはちみつ100%使用 健康 美容 低GI値 ギフト プレゼント マイハニー
体によさそうな雰囲気が出てるはちみつね。
焼いた豚肉に付けたらうまそう。
(7)JEAU CHAU スパイス セット 3種類 (カルダモン クローブ シナモン / 各50g) 選別品 香辛料 無添加 お試し ギフト
これを使ってスパイスカレーとか作ってみたい。
(8)【Amazon.co.jp 限定】ハウス やみつきスパイスペースト調味料セット(ハリッサ/サテトム/チポトレサルサ)【セット買い】
魅惑のハリッサ、楽園のサテトム、薫香のチポトレサルサ…味の想像ができないので気になるな。
オーガニック白ぶどうから醸造された有機白ワインビネガーと有機白ぶどう果汁を使い、伝統的な製法である濃縮、低温熟成、酢酸発酵をして丁寧に醸造された有機JAS認証の白バルサミコ酢…こういうのを使った料理を食いたい。
てんさい糖は賛否両論あるけれど、砂糖の代用としてありかもしれないね。
ふくさし、ふくちり専用に作られたぽん酢です。山口県萩特産の本だいだい果汁をたっぷり入れて香り高く、ふくを引き立てる味わいにしました。…ってね、ふぐを食う機会も金もないから、せめて…ポン酢で気分だけでも。
埼玉って醤油のイメージないけど、醸造所とかあるのね。
弓削多醤油、醤遊王国ってのも運営してる。
(13)湯浅醤油|魯山人醤油 200ml|高級さしみ醤油|奇跡の大豆・小麦から生まれた「奇跡の醤油」【本数限定販売】
魯山人が関西の薄口醤油を好んでいた、という嗜好にあわせて薄口醤油を目指し、薄い色に仕上げたいので木桶で8ヶ月(大手メーカーだと2ヶ月で完成させる)寝かせる。 一般的な薄口醤油より長く寝かせているためか醤油の色は濃いが、その分旨味成分が一般の醤油よりも1.6倍ほど高いものとなった。・・・いいね。この醤油で卵かけご飯を食ってみたい。
(14)ヤマロク 鶴醬 500ml
これも高級醤油か…木桶醤油だ。
江戸時代まで、こうした発酵調味料は全て「木桶」にて醸造されていました。ちなみに発酵調味料の全ては、乳酸菌や酵母菌などの「微生物たちの力」に よって造られます。人間が造るのではなく微生物が造るのです。よって人間(醸造家)の仕事は彼らが暮らしやすい、または居心地の良い環境作りのお手伝いを することです。つまり、彼らにとって最高に居心地の良い環境を創ってあげることができれば、最高においしいものができるというわけです。というわけで、な ぜ昔から木桶を使って来たかというと、そこにたくさんの微生物たちが暮らせる環境があるからであり、自然の力を借りるためです。おいしさの基本は、あくま で微生物たちが造り出す自然の恵みなのです。だからプラスティックの入れ物ではダメなんです。「木の桶」じゃないとダメなんです。
(15)吾妻食品 うまくて生姜ねぇ‼
ダジャレか…。
(16)キューネ バーベキューソースチポートレイバーガースタイル
なんかグルメバーガーの店とかに置いてそうなソースだ。
おつまみ・スイーツ
これも見た目の雰囲気がいい、美味しそう。
つまみ蔵、1968年からおつまみを販売している老舗みたいね。
これパッケージがいい。
(3)山形 土産 さくらんぼきらら (国内旅行 日本 山形 お土産)
美味しそうなゼリー。
(4)クランベリーハーフ 400g ドライ Dried Cranberry half モグーグ ドライフルーツ クランベリードライ 友口 tomoguchi もぐーぐ。 400g
クランベリー、健康によさそうな印象。食った方がいい気がする。
「もぐーぐ」ってメーカー名がかわいいな。
そういえば「もっもっ」って咀嚼音がキモいってまとめが最近、あったな。
食事してる時の効果音、「もぐもぐ」じゃなくて「もっもっ」って書いてある漫画が苦手→それすら超える異常咀嚼音シリーズが集まる
なんか生々しいからかな。
もぐもぐ、は逆にオブラートなのかもしれない。
これ食ってお茶で流し込んでダイエットしようかな…。
(6)源清田商事 有機むき甘栗 250g(125g×2袋入) 無添加 あまぐり おやつ スイーツ 和菓子
甘味料、香料、保存料を使ってない…いいな。
(7)うるわし茶房 きな粉デーツ [ 腸活 ダイエット ] デーツ きな粉 砂糖不使用 ドライフルーツ 和菓子 国内製造 無添加 農薬不使用 種なし スーパーフード (1袋)
きなこデーツ、味の想像ができないから食べてみたい。砂糖不使用なのもいい。
ブルボンのプチシリーズ、紅茶味とかあったのね。
(9)日昇堂 きぬにしき12個
日光東照宮献上菓子、徳川の家紋の包装紙に包まれて高級感がある、安いけど。
干し芋って焼きイモよりも高いから、なかなか買う気が湧かないんだよな。素材本来の甘味をアピールして、保存料や着色料が不使用っていうこの商品はよさそう。
(11)たらみ おいしい蒟蒻ゼリー ぶどう味 150g×6個
こんにゃくゼリー、マンナンライフの蒟蒻畑以外も食べてみたいなと。
(12)今川製菓 ジャイコン 塩コショウ味 大粒揚げトウモロコシ ジャイアントコーン 大容量 業務用(1kg)
ジャイアントコーンではなくジャイコーン。大粒のトウモロコシを揚げた…本当に大粒だ、トウモロコシの粒ってこんなに大きいのか。
(13)尾西食品 ミルクスティックプレーン 8本入×5個 (非常食・保存食)
カルシウム補給、骨が弱ってる爺さん婆さんや、骨粗鬆症とか予備軍の人にお勧めかもだ。
名古屋土産、アマゾンで買えるじゃん。しかも販売元がAmazonだからAmazon公式が販売しているということ、転売とかじゃないので安心。
(15)山盛堂本舗 サラダ小僧 255g
あられ、最近食ってないな。
1977年創業のドイツのキャンディーメーカー、カベンディッシュ&ハーベイ。果実そのものを食べているかのようなみずみずしくピュアな味わいが特徴です。・・・容器もオシャレ、インテリアとして置いておくのもよさそう。
Amazonの本気、楽天でも売ってるけど。
プライム感謝祭はだいぶ安くなってる。
(17)iSDG 医食同源ドットコム しいたけスナック うま塩味 70g 真空フライスナック (8袋)
ポテチ食うより、こういうの食った方がいいんだろうなぁ。
その他
(1)森永乳業 1食分のやさいジュレ 70g×6個 (2種類×3個) [ 1歳頃から たっぷり緑黄色野菜とくだもの 20種類の野菜とくだもの 詰め合わせ 着色料 香料 保存料不使用 ゼリー飲料 ]
野菜ジュレ、栄養補給によさそう。子ども向けか?
(2)アメ横 大津屋 ムング ホール 緑豆 リョクトウヤエナリ 八重生 青小豆 文豆 もやし 豆 まめ 皮付き ムング moong dal 2.5kg
ムングホール、ウズベキスタン産の食べ物がAmazonで買える。美味しいかどうかは不明。
(3)高鍋商事 特選大豆 ( 1kg ×1袋 ) 北海道 とよまさり ( チャック付き ) 乾燥大豆 ( 大容量 / 大粒 ) 大豆屋 / 国産 大豆
これもムングホールと同じくプロが買うのかな?
この大豆から、大豆肉とか豆腐とか作れるのかなぁ。
あ、レビュー読むと味噌とか作る人がいるみたいだ。
(4)【2023モンドセレクション金賞受賞】 オリゼ 米麹グラノーラ プレーン 200g グラノーラ 糖質オフ 砂糖不使用 無添加 甘酒グラノーラ 低カロリー 腸活 低糖質グルテンフリー 糖質カット 砂糖0 低GI おきかえ シリアル オートミール
米麹グラノーラ、白砂糖も人工甘味料も不使用みたいなので食ってみたい。
カルビーのフルーツグラノーラ好きなんだけど、あれ健康にあんまよさそうなイメージないんだよな…甘いから糖分多そうだし。
(5)友盛貿易 中国産 油葱酥(フライドエシャロット) 500g
フライドエシャロット、天かすみたいな?体によさそうなイメージはない。
(6)日食 オーガニックコーンフレーク ビターカカオ 200g×5個
コーンフレーク、オーガニックなイメージないから、食べてみたい。
カブをキムチ風にしてるのね。おつまみとしては何に合うのかイメージが湧かない…。
以上、気になる食いものはこんなところか。
結構、列挙した。
節約グルメアイテムを集めるつもりが、贅沢品もちらほら、むしろそっちの方が多いか。
あと、お金があれば、LEPOREMのバスボムとか、風呂に入れてみたい。
お経読む時に楽ができそうな楽々正座いすと、座りながら草抜きができそうなフィールドカートとかいうのも、一台ぐらいあってもいいな。
伊丹空港にあった座り心地がいい椅子も欲しい。
AKRacing ゲーミングチェア 計52脚を 大阪国際空港(伊丹空港) 出発・到着フロア 搭乗待合室に導入 フライト前の待ち時間を快適に過ごせる空間を提供
Pro-X V2シリーズか。伊丹空港ですごい座り心地いい椅子があったから「これ欲しいなぁ~」と思ったんだよな。5万円台…ANAのトクたびマイルでしか飛行機に乗れない、低所得者の自分には値が張るが…いつか買いたい
2024/10/16 23:40
ああ、欲しいもの並べたけど、全部は買えないな。
基本的には家賃と食費、それだけに費やすのが自分は限界だけど…いつかここに書いたやつを全部買いたい…置く場所がないけど。
電車内の車内広告で流れていたスーパーマリオパーティジャンボリー?とかいうゲームのCMに、疎外感を感じた。
こんな広いリビングで、身体動かすゲームとか出来る生活してる人ってどれぐらいいるんだろう…自分はこんな家に住めることはないんだろうなぁ。